SNSなどでも回ってくる動画「馬の装蹄」つい目を止めてしまい、 ずっと見てしまいます!!!
馬の爪切り気持ちいい動画
鉄を取ってから、ゴミを取り除き、爪を削ぎ、爪を切り、 ヤスリをかけるところがとても好きです!!!気持ちいい!!道具を無駄なく使う感じの手際の良さも見ていてスッキリします。

最近はミニチュアホースなど、小型のお馬さんも増えており、 ペットとしてお馬さんと一緒に暮らすかたもいらっしゃいます。
馬は体重およそ300kgに対し、牛は大きいと1000kgある個体もあったりなど、 大きさが全然違います。お馬さんでも大変そうなのに、 牛さんの削蹄時の保定は、なかなか大変そうですよね。

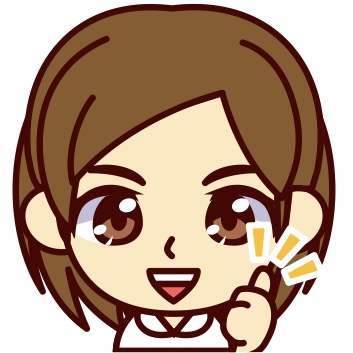
おわりに
犬も猫はもちろん、牛も馬も、家畜化され、現在では野生よりも人と暮らす方が多いです。
人に飼われるために改良され、人のケアがないと体調を崩す原因になってしまう 動物に変わってしまいました。
家畜であろうとペットであろうと、愛情を持って、不潔な状態にせず、 健康な状態を維持できるようしっかりお手入れはしましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました!
1頭あたり30分〜1時間と考えると、犬のトリミングよりは少し高いか同じぐらいですかね? これだけの重労働でと考えると安い気がしてしまいました!

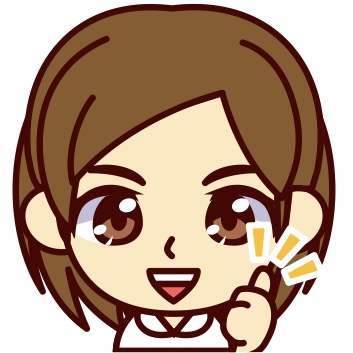
飼育放棄されたポニー
こんな記事を見つけました。装蹄を10年間されず、 まともに歩くことができない状態で、栄養失調になっていたポニーが保護されました。ろくに動くこともできず、爪を放置しているとこのように螺旋を描くように伸び、 歩けなくなってしまうのですね・・・

牛にも装蹄があった!
牛さんはお馬さんとは逆で、蹄が伸びすぎてしまうため、 昔はお馬さんの装蹄と同じように牛さんにも装蹄をしていたようです。 今では、削蹄(さくてい)と呼ばれる、爪切りのようなものだけが行われています。
牛さんの場合は年に2回程度なので頻度としては少ないですが、 健康のために必要です。お馬さんのやり方に似ているように見えますが、別物です。
日本ではナイフのようなもので爪を削ぎ落としながらやっていきますが、 海外のもので、牛が四つ足浮いている状態になる機械に入れて、 電動ヤスリのようなもので、削いでいる動画をみました!7分ぐらいから見れます!犬のおやつに牛の蹄がありますが、あの蹄に釘を打ち付けてるイメージですね! ちなみに蹄を犬にあげると、歯は綺麗になりますが、歯が折れますのでご注意を!
馬は体重およそ300kgに対し、牛は大きいと1000kgある個体もあったりなど、 大きさが全然違います。お馬さんでも大変そうなのに、 牛さんの削蹄時の保定は、なかなか大変そうですよね。

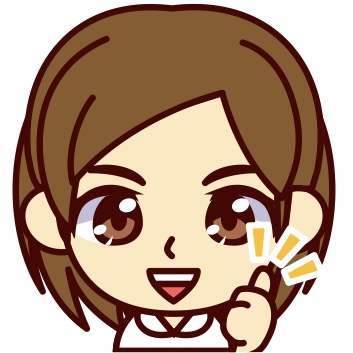
おわりに
犬も猫はもちろん、牛も馬も、家畜化され、現在では野生よりも人と暮らす方が多いです。
人に飼われるために改良され、人のケアがないと体調を崩す原因になってしまう 動物に変わってしまいました。
家畜であろうとペットであろうと、愛情を持って、不潔な状態にせず、 健康な状態を維持できるようしっかりお手入れはしましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました!
海外ではミニチュアホースが盲導犬の役割をすることもあるそうですよ!

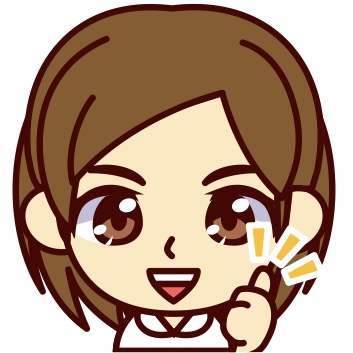
馬の蹄は第二の心臓
お馬さんは、脚が骨折するだけで安楽死になってしまう動物です。 蹄はお馬さんにとって「第二の心臓」とも呼ばれるほど、大変重要な役割を持っています。 蹄の状態で健康状態が変わったりなど、まさに健康のバロメーターですね。
野生のお馬さんの蹄は、良い具合にすり減ってくれていたのですが、 家畜化されたことで、野生時代よりもすり減りやすくなってしまったそうです。 これでは蹄(ひづめ)がすり減りすぎてしまい、深爪のような状態になってしまいます。
そこで人間が考えついたのがこの「装蹄」です。
私は逆に伸び続けてしまうから装蹄するのかと思ったので意外でした!
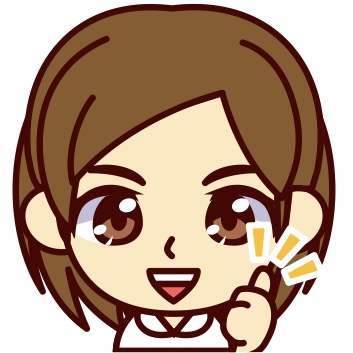
装蹄はお馬さんのお靴のような役割で、成長期のバランスを補ったり、 怪我や病気の予防もできてしまう、馬の健康のためによく考えられたものでした。
馬の靴職人=装蹄師
いわばお馬さんの靴職人さんを、「装蹄師」さん(そうていし)と呼びます。 装蹄師さんは住み込みで学び、修行をします。
お馬さんが突然嫌がり暴れることがあるため、装蹄師さんであっても、 事故は起きます。蹴られたり踏まれたりすることがあるので、命懸けの作業です。

蹄は1ヶ月に1cm程度伸びるので、競走馬では2〜3週間ごと1回、 乗用馬では、1ヶ月〜1ヶ月半に1回調整をします。
1頭あたり30分〜1時間の時間がかかります。
競走馬は軽量のアルミ製の蹄鉄(ていてつ)を使うので摩耗しやすいため頻度が短いです。
足が4本あるので大変ですが、お馬さんの健康のためには欠かせないですね。

痛くないの?
熱々の鉄を蹄に当てて物凄い煙が出ている動画や、 蹄に直接釘を打つ様子を見ていると、痛くないのかと思ってしまいますが、 お馬さんは全然気にしていない様子を見て、不思議だなと思っていました。
人間の爪は薄く同じことをしたらとても熱そうですが、 お馬さんは爪の部分が非常に大きいため、装蹄は特に熱くもなければ痛くないことです。
蹄鉄(ていてつ)と呼ばれる、蹄につける鉄のようなものは、 1頭1頭形が違うので、熱した鉄を1つ1つ金槌で叩いて調整して作ります。
手作業で職人さんお一人でやっているので、気の遠くなる作業に感じてしまいます。 しかしお馬さんの健康のためと思ったらやりがいのあるお仕事ですね!

装蹄はいくらかかるの?
競走馬の場合1頭あたり1万円〜2万円、乗用馬の場合1万円〜1万5千円程度です。 地域や馬の用途により異なります。
1頭あたり30分〜1時間と考えると、犬のトリミングよりは少し高いか同じぐらいですかね? これだけの重労働でと考えると安い気がしてしまいました!

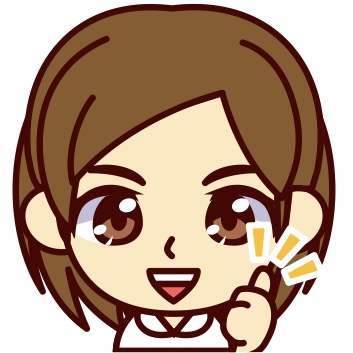
飼育放棄されたポニー
こんな記事を見つけました。装蹄を10年間されず、 まともに歩くことができない状態で、栄養失調になっていたポニーが保護されました。ろくに動くこともできず、爪を放置しているとこのように螺旋を描くように伸び、 歩けなくなってしまうのですね・・・

牛にも装蹄があった!
牛さんはお馬さんとは逆で、蹄が伸びすぎてしまうため、 昔はお馬さんの装蹄と同じように牛さんにも装蹄をしていたようです。 今では、削蹄(さくてい)と呼ばれる、爪切りのようなものだけが行われています。
牛さんの場合は年に2回程度なので頻度としては少ないですが、 健康のために必要です。お馬さんのやり方に似ているように見えますが、別物です。
日本ではナイフのようなもので爪を削ぎ落としながらやっていきますが、 海外のもので、牛が四つ足浮いている状態になる機械に入れて、 電動ヤスリのようなもので、削いでいる動画をみました!7分ぐらいから見れます!犬のおやつに牛の蹄がありますが、あの蹄に釘を打ち付けてるイメージですね! ちなみに蹄を犬にあげると、歯は綺麗になりますが、歯が折れますのでご注意を!
馬は体重およそ300kgに対し、牛は大きいと1000kgある個体もあったりなど、 大きさが全然違います。お馬さんでも大変そうなのに、 牛さんの削蹄時の保定は、なかなか大変そうですよね。

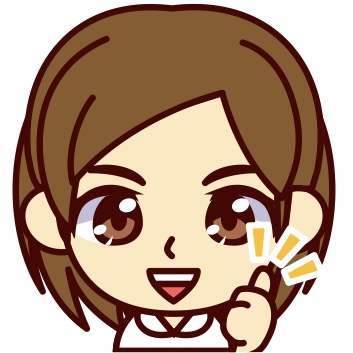
おわりに
犬も猫はもちろん、牛も馬も、家畜化され、現在では野生よりも人と暮らす方が多いです。
人に飼われるために改良され、人のケアがないと体調を崩す原因になってしまう 動物に変わってしまいました。
家畜であろうとペットであろうと、愛情を持って、不潔な状態にせず、 健康な状態を維持できるようしっかりお手入れはしましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました!
海外ではミニチュアホースが盲導犬の役割をすることもあるそうですよ!

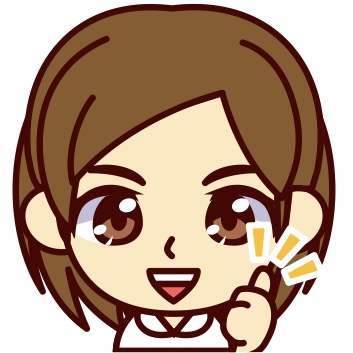
馬の蹄は第二の心臓
お馬さんは、脚が骨折するだけで安楽死になってしまう動物です。 蹄はお馬さんにとって「第二の心臓」とも呼ばれるほど、大変重要な役割を持っています。 蹄の状態で健康状態が変わったりなど、まさに健康のバロメーターですね。
野生のお馬さんの蹄は、良い具合にすり減ってくれていたのですが、 家畜化されたことで、野生時代よりもすり減りやすくなってしまったそうです。 これでは蹄(ひづめ)がすり減りすぎてしまい、深爪のような状態になってしまいます。
そこで人間が考えついたのがこの「装蹄」です。
私は逆に伸び続けてしまうから装蹄するのかと思ったので意外でした!
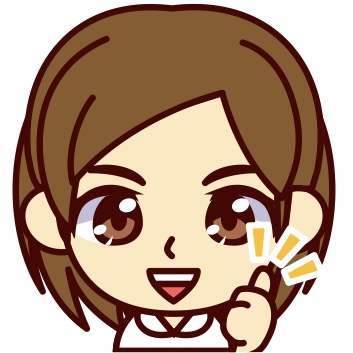
装蹄はお馬さんのお靴のような役割で、成長期のバランスを補ったり、 怪我や病気の予防もできてしまう、馬の健康のためによく考えられたものでした。
馬の靴職人=装蹄師
いわばお馬さんの靴職人さんを、「装蹄師」さん(そうていし)と呼びます。 装蹄師さんは住み込みで学び、修行をします。
お馬さんが突然嫌がり暴れることがあるため、装蹄師さんであっても、 事故は起きます。蹴られたり踏まれたりすることがあるので、命懸けの作業です。

蹄は1ヶ月に1cm程度伸びるので、競走馬では2〜3週間ごと1回、 乗用馬では、1ヶ月〜1ヶ月半に1回調整をします。
1頭あたり30分〜1時間の時間がかかります。
競走馬は軽量のアルミ製の蹄鉄(ていてつ)を使うので摩耗しやすいため頻度が短いです。
足が4本あるので大変ですが、お馬さんの健康のためには欠かせないですね。

痛くないの?
熱々の鉄を蹄に当てて物凄い煙が出ている動画や、 蹄に直接釘を打つ様子を見ていると、痛くないのかと思ってしまいますが、 お馬さんは全然気にしていない様子を見て、不思議だなと思っていました。
人間の爪は薄く同じことをしたらとても熱そうですが、 お馬さんは爪の部分が非常に大きいため、装蹄は特に熱くもなければ痛くないことです。
蹄鉄(ていてつ)と呼ばれる、蹄につける鉄のようなものは、 1頭1頭形が違うので、熱した鉄を1つ1つ金槌で叩いて調整して作ります。
手作業で職人さんお一人でやっているので、気の遠くなる作業に感じてしまいます。 しかしお馬さんの健康のためと思ったらやりがいのあるお仕事ですね!

装蹄はいくらかかるの?
競走馬の場合1頭あたり1万円〜2万円、乗用馬の場合1万円〜1万5千円程度です。 地域や馬の用途により異なります。
1頭あたり30分〜1時間と考えると、犬のトリミングよりは少し高いか同じぐらいですかね? これだけの重労働でと考えると安い気がしてしまいました!

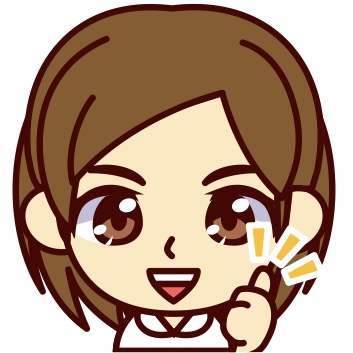
飼育放棄されたポニー
こんな記事を見つけました。装蹄を10年間されず、 まともに歩くことができない状態で、栄養失調になっていたポニーが保護されました。ろくに動くこともできず、爪を放置しているとこのように螺旋を描くように伸び、 歩けなくなってしまうのですね・・・

牛にも装蹄があった!
牛さんはお馬さんとは逆で、蹄が伸びすぎてしまうため、 昔はお馬さんの装蹄と同じように牛さんにも装蹄をしていたようです。 今では、削蹄(さくてい)と呼ばれる、爪切りのようなものだけが行われています。
牛さんの場合は年に2回程度なので頻度としては少ないですが、 健康のために必要です。お馬さんのやり方に似ているように見えますが、別物です。
日本ではナイフのようなもので爪を削ぎ落としながらやっていきますが、 海外のもので、牛が四つ足浮いている状態になる機械に入れて、 電動ヤスリのようなもので、削いでいる動画をみました!7分ぐらいから見れます!犬のおやつに牛の蹄がありますが、あの蹄に釘を打ち付けてるイメージですね! ちなみに蹄を犬にあげると、歯は綺麗になりますが、歯が折れますのでご注意を!
馬は体重およそ300kgに対し、牛は大きいと1000kgある個体もあったりなど、 大きさが全然違います。お馬さんでも大変そうなのに、 牛さんの削蹄時の保定は、なかなか大変そうですよね。

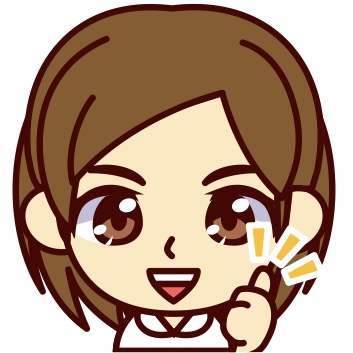
おわりに
犬も猫はもちろん、牛も馬も、家畜化され、現在では野生よりも人と暮らす方が多いです。
人に飼われるために改良され、人のケアがないと体調を崩す原因になってしまう 動物に変わってしまいました。
家畜であろうとペットであろうと、愛情を持って、不潔な状態にせず、 健康な状態を維持できるようしっかりお手入れはしましょう。
最後までお読みくださりありがとうございました!
